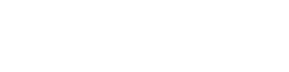桃の節句は春のおとずれ
桃の節句は女の子のお祭り
3月3日はひな祭り。子供の頃に、「うれしいひなまつり」という歌を必ず歌ったものです。(今はどうなの?)
”明かりをつけましょぼんぼりに、お花を上げましょ桃の花”・・・「ぼんぼり」なんて知らない人も多いのかもしれませんね。
豪華なお雛様を飾るお家は少なくなったと思いますが、東京では、ホテルのロビーなどで見ることが出来ます。デパートもいいですね。
春の到来を感じさせる華やかなひな祭りは、なんとなくこころがウキウキするものです。

節目を祝う日本の行事
時間には区切りがあります。
1日は24時間、1週間は7日。一年は12か月。。。等々。
国や宗教によっても時の括りは変わってくるものだと思います。
日本の宗教は?と聞かれて、実は答えられる日本人は割合に少ないかもしれません。
神様は信じているけれど、神様の概念って日本ではかなりユニークなもので、海外の人にはなかなか理解が難しいものだと思います。
ひな祭りは、神道の5節供の一つ。
もともとは中国の道教の儀式が日本に伝わり、奈良時代に日本古来の儀礼や祭礼などと結びつき、宮中で邪気を祓う行事が催されるようになったと言われています。
1年を割り切れない5で区切って節供の行事としています。
1月7日の七草がゆの節供
3月3日の桃の節句、これがひな祭りです。
5月5日の端午の節供 子供の日で休日です。
7月7日の七夕の日。
9月9日重陽の節供 菊祭りが開かれます。
よく、「ハレの日」と言いますが、こうした特別のお祝いの行事はまさに「ハレの日」。特別な装いをして、神様に供したお食事を下げて皆で食べた風習がありました。
お正月なども良い例ですが、お正月に晴れ着を着てお年始なんて風習はもう殆ど見ないですよね。
「ハレの日」に対しての日常は「ケの日」といいます。
日本の人々はこの言葉を使って日常生活にメリハリをつけていました。

吊るし雛の愛らしさ。
ひな人形を飾るというのは、江戸時代頃から豪華になったからで、もともとは人形(ヒトガタ)を人に見立て穢れを祓うことを目的にしていたもので、川に流していたもの。災いや悪から守るための身代わりのものでした。そうそう、「千と千尋の神隠し」にハクの周りを飛んでいたのも人形でしたね。
紙で人の形をくりぬいて、厄除けにしていたのが始まりです。
一般庶民はとても豪華な雛人形なんて買えなかったので、女性たちが、古着などを持ち寄って、日常の道具や、動物、そして子供たちの健やかな成長を祈って愛らしい人形たちを縫い、部屋や軒下に吊るしたのが吊るし雛の始まり。
お道具や十二支にまつわり動物たちや子供たちが多いのは、健やかな子供の成長と、幸せな結婚を意味するところが大きいと思います。
時代は変わり、結婚の概念も変わりまして、女の子は幸せな結婚をして子供を産んでなんて定説ではなくなりましたが、この吊るし雛のアイテムは愛らしくて、ずっと見ていて飽きません。
手仕事で作られているので、それぞれに作者の個性が溢れています。
なにもかも早く変わってしまう世の中ですが、どこかほっとするゆったりとした時間が感じられます。
そしてお節句には神様に供した特別の食事を下げて家族で食べるという「節供」の意味合いもあります。
ひな祭りは、色とりどりの具をちらした「ちらし寿司」が定番です。お菓子もカラフルな雛あられを食べますよね。まさに春のお祭りです。
そんな華やかな食卓は、女の子だけのものではないですよ。

Plan your own trip to Tokyo, that's "My Tokyo"
Our friendly guides will help you make your dreams come true.
Make your own Tokyo with your favorite places and new discoveries!
Tours start from 2 hours. Home-cooked meals and cultural experiences are also available!
An authentic experience is here.

自由に旅をしたい。
旅行に行きたいと思ったら、まずパッケージから探すあなた。
そこから、自分ならこうしたいのにと考えることありませんか?
旅行会社はパッケージを作るばかりではありません。専門のスキルを活かして、価値のある個人旅行の作り方をアドバイスします。
まるっと手配を頼むのも旅行会社だけが出来ること。
自分で手配をするのなら、そのノウハウもお教えします。
旅は自分の財産になる体験です。ぜひ一度セミナーにお越しください。